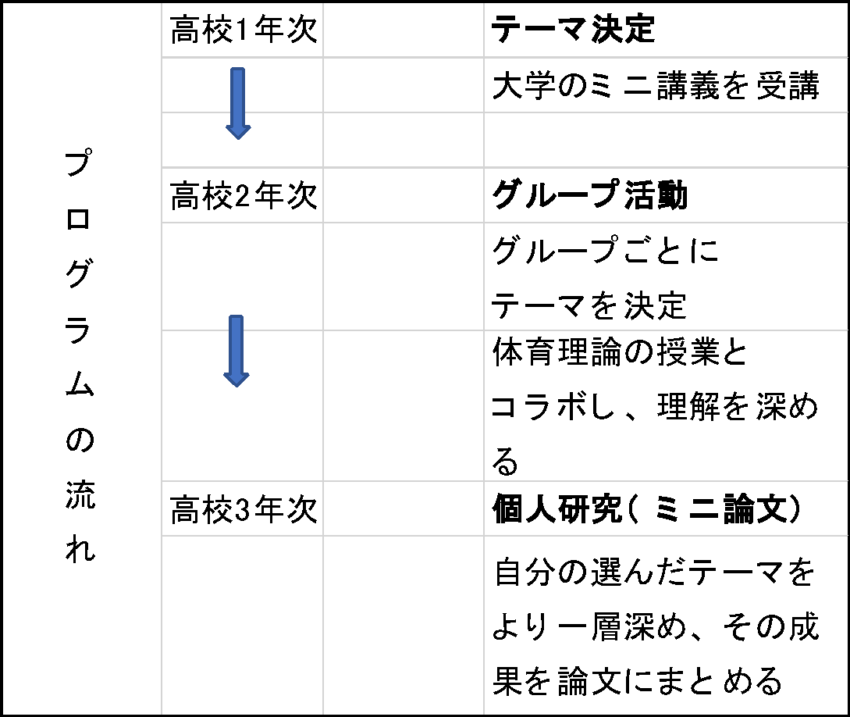【最優秀賞】小児を対象としたユーモアクッションの開発
<研究内容>
土佐市にある児童発達支援事業所から、遊べて、リラックスのできるクッション製作の依頼を受けた。クッションを製作するにあたり、施設に通う発達障害児5名(男性4名・女性1名)を調査対象とした。施設環境の調査後、今までにないクッション、ユーモアクッションに求められる要素を抽出した。1200×170(mm)、周径550(mm)の円柱型のクッションを5つ製作し、学生による試用評価後、対象者による1週間の試用評価と施設職員に対してアンケート調査を実施した。クッションの使い方や遊び方を考えて楽しんでもらえた反面、大きさや形状により収納性が低い点、小さい子どもにとっては高さがあり危険な点などが改善点として挙げられた。いくつかの改善点があるものの、遊び方の種類や汎用性が高く、対象者のユーモアや遊び心を引き出すことができるクッションとなった。
(担当教員:岩﨑 洋)学生7名
【優秀賞】土佐市の横断歩道における青信号点灯時間の調査(第2報)〜高知県全域を調査して〜
<研究内容>
高知県の高齢化率は全国2位であり、高齢者が極めて多い地域である。令和3年度は県内の交通事故死者に占める高齢者の割合が84%で全国ワースト1位であり、高齢者の事故予防は地域の取り組むべき課題であるとも言える。調査対象箇所は、室戸市から四万十市に至る高知県内全域の国道および県道における信号機のある横断歩道174箇所とした。それぞれの横断歩道における青信号点灯時間と横断歩道の距離を測定し、その値から歩行者が横断可能な歩行速度を算出した。結果、高知県下の横断歩道は比較的横断時間に余裕のある設定であり、10mを12秒以内で歩行可能であれば青信号点灯中に横断が可能であることが明らかとなった。高齢者の歩行速度を知る理学療法士による交通安全指導は、高齢者の事故予防の一助になると考えられる。
(担当教員:柏 智之)学生7名
【優秀賞】小学生の体格の意識と生活習慣との関連について-幼児期と現在の生活習慣の比較-
<研究内容>
人の体脂肪率は3歳までの食習慣で決まると言われており、令和5年度第1回土佐市子どもの健康づくり支援委員会資料によると、小学生高学年の肥満傾向は、男女ともに近年は増加傾向にあることが明らかになっている。土佐市内の小学生に対して個人の体格や幼児期・現在の生活習慣に関するアンケートを実施し、体格の意識と生活習慣との関連を検討した。対象は土佐市内のA・B小学校の2校4・5・6年生285名とした。結果、自身の体格の意識が実際の体型と一致していない児童は今の生活で好き嫌いなく何でも食べるが、運動は好まないという傾向であった。児童期をより健康な状態で過ごし発達するためにも、客観的な体型の把握や親子への生活指導が重要であると考えられる。
(担当教員:重島晃史)学生7名
【テーマ一覧】
〇 災害時の避難における移動支援機器開発の経過 ~津波避難タワー攻略編~
(担当教員:有光一樹・金久雅史)学生5名
〇 高齢者運転による交通事故の現状と事故防止策の提言
(担当教員:田頭 勝之)学生6名
〇 公園における遊具標識の実態調査 ~子供に対するアプローチ~
(担当教員:吉村知佐子)学生4名
〇 地域在住高齢者の携帯電話に関する困りごと
(担当教員:光内梨佐)学生5名
〇 障がい者支援施設における腰痛症対策 -いつでもどこでも簡単に!-
(担当教員:宮﨑登美子)学生6名
〇 免許返納する・しないの理想と現実
(担当教員:石川裕治)学生5名
〇 薬物依存歴を持つ女性の健康状態に関する研究
(担当教員:足立 一)学生5名
〇 子ども食堂の現状について ~実地調査とアンケート調査より~
(担当教員:辻 美和)学生5名
〇 小学生の登下校について ~保護者へのアンケート調査より~
(担当教員:篠田かおり)学生6名
〇 地域在住高齢者の余暇活動が健康にもたらす影響
(担当教員:笹村 聡)学生5名
〇 絵本の読み聞かせと子育てに関するアンケート調査 ~絵本で困りごとを軽減しよう~
(担当教員:池 聡)学生5名
〇 高齢者擬似体験システムを用いた土佐市避難タワーの避難想定
(担当教員:平賀康嗣)学生7名
〇 高校サッカー選手における足部アライメントと足関節捻挫の関係 〜入学時のフィジカルチェック結果と3年間の 足関節捻挫について~
(担当教員:片山訓博)学生6名
〇 小学生の外遊びの時間と体力の関係 -10年間の変化-
(担当教員:栗山裕司)学生6名
〇 小学生野球チームに対する野球ひじ検診実施報告
(担当教員:相澤 徹、大塚貴英)学生6名
〇 がんロコモの現実 -在宅リハビリテーションの新たなフロンティア-
(担当教員:明崎禎輝)学生4名